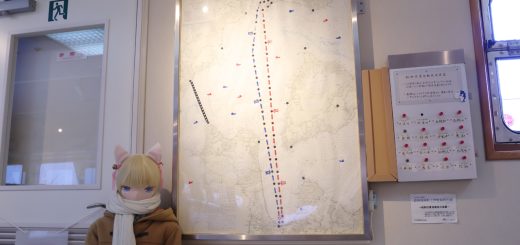青函連絡船出航時の船橋機器操作要領③(出航)
本サイトの記事にはアフィリエイト広告が含まれますが、記事の内容は中立性を保つ様、細心の注意を払って編集しております。

今回は船長が「長声一発」とオーダーをしたところから解説していきたいと思います。この「長声一発」のオーダーで汽笛を鳴らしますが、連絡船ではこの汽笛を鳴らした時間を出航時刻として記録していました。
船長が「長声一発」と指示したら航海係が「長声一発・サー」とアンサーバックして汽笛を鳴らします。長声の汽笛は5秒鳴らします。今回の解説の多くは三等航海士の仕事内容ですが、ここは航海掛(操舵手)の役割です。
三等航海士は時刻を確認して「出航定時でした」または「出航定時・サー」と報告します。1分以上前後した時は「1分延」「1分早」と報告していたと思いますが、10秒程度の前後は定時と報告していたと記憶します。時計はこの手元にある写真の時計でも構いませんし、前方上側にも時計がありますのでどちらの時計を見ても構いません。
ちなみに船舶内では時計は電気で動いていますが、電池を使った同じ見た目の市販品が「防塵時計」という名称で販売されています。我が家でも連絡船終航の時に買いましたが、35年以上経った今も普通に動いています。なかなかタフな時計です。

セイコークロック(KS474M)防塵型(Amazon)
他の取扱店:楽天市場
函館発は出航と同時に船を右に振って桟橋と直角に進んで行きますので、船長の最初のオーダーは「バウ・ライト」でした。バウスラスターのハンドルを右15度に設定します。少し遅れて前側の指示器も15度を指し示します。
この時点では後ろ側のプロペラはまだ作用していませんが、バウスラスターが動くと船の前方が右側に振れていきます。船が少しずつ岸壁から離れていよいよ函館桟橋を後にします。
函館発では約15秒後に「スローアヘッド・ポート」と船長からオーダーが入りますので、「スローアヘッド・ポート」と復唱して左舷側の可変ピッチプロペラをS▶と書かれた7度の位置に持っていきます。そして操作が終わったら「スローアヘッド・ポート・サー」と報告します。
次に「スローアヘッド・スターボード」とオーダーが入りますので「スローアヘッド・スターボード」と復唱して今度は右舷側の可変ピッチプロペラをS▶と書かれた7度の位置に持っていきます。ここで注意点は現時点で両舷共「スローアヘッド」になったので「スローアヘッド・ツーエンジン・サー」と報告します。この時のアンサーバックは「スローアヘッド・スターボード・サー」ではありませんでした。
また私が指で押さえている部分を回すとレバーをゆっくり動かすことが出来ますので、角度の微調整が出来ます。上のボタンを押してサッとレバーを動かして、つまみを回して微調整をする様な方法で角度をセットしていました。
次回は最終回としてリングアップエンジンまでと三等航海士の機器操作と並行して行われているお仕事について解説していきたいと思います。
 青函連絡船物語 |
 海峡の鉄路 青函連絡船 110年の軌跡と記憶 |
 青函連絡船 乗組員たちの証言 (イカロス・ムック) |
 鉄道連絡船細見 |
 鉄道連絡船のいた20世紀 |
| 住所 | 〒040-0063 北海道函館市若松町12番地先 |
| ホームページ | 函館市青函連絡船記念館摩周丸 |
| 近くの宿を探す |